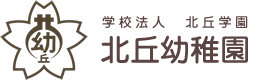4月に行われた全国学力テストと合わせて行われた児童生徒へのアンケート調査で「勉強の好き嫌い」や「授業への理解度」などの項目で、初めて、男女別の集計をしました。「算数の勉強は好きだ」という質問に小学男子は「どちらかといえば」を含めて「当てはまる」と回答した児童が67.3%、女子は48.6%と18.7%の差が見られました。一方国語の方は、中学校も含めて、女子の方が高かったそうです。文部科学省では、女子だから理系が苦手、文系のほうがいいといった「アンコンシャス・バイアス」が幼いころから周囲にあり、本人に影響しているのではないかと分析しています。
「アンコンシャス・バイアス」とは、私たちが過去の経験や社会的な刷り込みによって、無意識のうちに「こうあるべき」と思い込んでしまう心のクセのことです。「ピンクは女の子の色」「力仕事は男の人がするもの」。お手伝いを頼むとき、つい「お兄ちゃんは力仕事」「妹は料理のお手伝い」と役割を分けてしまう。遊び道具を選ぶとき、「これは男の子向け」「これは女の子向け」と決めつけてしまう。子どもが「○○になりたい」と言ったとき、「それは男の子の仕事だよ」と否定してしまうなどなど。
こうした言葉は、子どもたちの「やってみたい」「なりたい」という気持ちにブレーキをかけてしまいかねません。アンコンシャス・バイアスは誰にでもあるといわれています。大切なのは、それに「気づこうとする姿勢」です。「これは私の思い込みかもしれない」と立ち止まることで、子どもたちの可能性を広げることができます。子どもの言葉や行動を性別や年齢で判断せず、個性として受け止める。「ふつうはこう」と言いたくなったとき、自分の中の“ふつう”を問い直してみる。家族の中で、役割を柔軟に分担し、子どもが多様な経験をできるようにする。
子どもたちは、私たち大人の言葉や態度から多くを学びます。私たち自身が「思い込み」に気づき、柔軟な心で接することが、子どもたちの未来を豊かにする第一歩になります。