
11月6日松戸市民劇場にて第37回松戸市幼児教育振興大会が私立幼稚園連合会、私立幼稚園連合会父母の会の主催で開催されました。この大会は、幼稚園設置者、園長と園児の保護者及び行政の担当者が一堂に会し、幼児教育の質の向上、補助金の増額、保護者の教育費負担軽減等の実現を目指して、行政機関に要望を上げる会です。今年度は、北丘幼稚園からも6名の保護者の方が参加してくださいました。役員の一人として大変ありがたかったです。
セレモニーの後、桜花学園大学教育保育学部学科長の寺田 泰人先生から「子どものスポーツ活動が育む健やかな成長」というテーマで記念講演がありました。先生は長年にわたり子どものスポーツ活動について研究、指導されてきた方です。私自身も長年小学校体育に携わってきた一人ですので、興味深く拝聴させていただきました。概要は以下の通りです。
日本の子どもの体格(身長や体重)は、大きくなっているが、体力は1980年代をピークに低下傾向が続いている。幼児期に神経系統は8割が完成すると言われているが、「すわらないと靴が履けない」「階段の降り方がぎこちない」「転んだ時に受け身がとれず、けがをしてしまう」「鬼ごっこをしていて、鬼から上手に身体をかわすことができない」などの現状が見られる。要するにバランスに関わる身のこなし方が懸念される。2023年7月に行われた幼稚園教諭を対象にしたアンケート調査によると、運動に対して苦手意識のある園児が一定数いると約60%が回答している。その原因は、コロナ禍の影響というよりもスクリーンタイムの長さと考えている教師が多い。早期にスポーツを経験させることのメリットもあるが、デメリットもある。家庭の経済的・時間的な状況もあり、幼稚園で運動遊びを保証する必要がある。また、自発的な運動の機会つまり自由遊びが大切である。幼児における運動の意義について幼児期運動指針では、①体力・運動能力の基礎を養う。②丈夫で健康な体になる。③意欲的に取り組む子どもになる。④協調性やコミュニケーション能力が育つ。⑤認知能力の発達にも効果がある。と記されている。
文部科学省では、子どもの体力低下の原因を「三間の減少」にあると説明しています。三間とは「時間」「空間」「仲間」のことです。幼児期に外遊びで身体を動かす習慣を身につけることができるかどうかが小学校以降の運動習慣の基礎になり、体力向上の要因となります。北丘幼稚園では、子ども達にたくさん外遊びをさせて、健康で活力のある子どもを育みたいと思います。
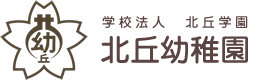

.jpg)

