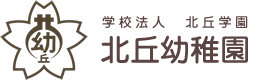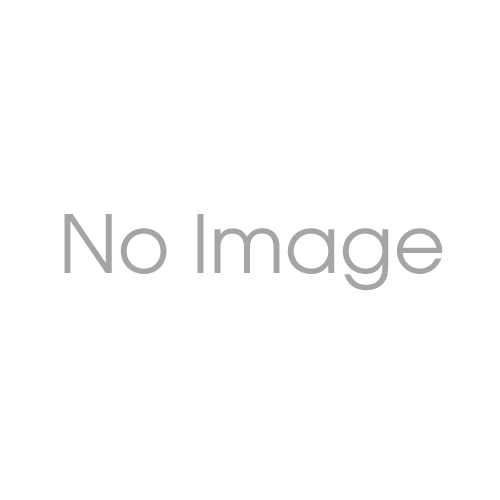
表題は、令和6年度松戸市教育委員会主催の家庭教育講演会の演題です。講演者は、東北大学加齢医学研究教授の川島隆太先生です。川島先生は、脳トレで有名な方ですが、松戸市版幼児家庭教育パンフレットの監修者であり、市内各所で講演会を開催しています。先日、川島先生の講演会に参加する機会がありました。先生のお話を聞くのは2度目となりますが、いつお聞きしてもハッとさせられるお話ばかりです。今回は、一般の方に交じって中学生、小学生も参加していました。子ども達の生活習慣の改善につながることを期待してやみません。
さて、話の内容ですが、脳の説明の後、大きく分けて「睡眠」「食事」「運動」の3つのお話がありました。かいつまんで記したいと思います。まずは、睡眠です。夜更かしは、生活のリズムを崩し、心にも体にもよくありません。エネルギーを生み出すミトコンドリアの機能が低下し、疲れやすくなり、学力や体力の低下を引き起こします。睡眠が足りているかどうかは、①朝の目覚めがよいか。②休みの日も同じ時刻に起きることができるか、でわかります。子どものころから睡眠時間が足りていないと、50代後半でアルツハイマーになってしまうことが懸念されます。早寝は、子どもたちの心身の発達に必須です。小学生であれば遅くとも9時に寝かせましょう。
次に「食事」です。朝食が大事で、朝食の質が大人に成長した後も人生に影響することも忘れてはいけません。朝食でおかずをしっかりとらないと、大学受験も就職もうまくいかず、年収も低くなります。また、家族そろって朝食を食べないと、意欲が育たないこともわかっています。
3つ目に「運動」です。筋肉は使わないと一気に衰えます。幼児期に身体を動かすいろいろな遊びをしていた子どもは、いつも同じ遊びしかしていなかった子に比べて、体力総合点が高い傾向にあります。また、手を使って文字を書いたほうが、パソコンを打つよりも脳が働きます。辞書を引くことは、スマホで調べるより脳が働きます。動画サイト視聴に至っては、脳が寝ている状態です。そして、読書は脳の全身運動です。創造力を伸ばすために紙の本を読むのがよいでしょう。読書をすると、脳が発達します。
最後に質問を受ける時間がありました。中学生から的を得た質問がたくさんありました。その中で、「頭のいい悪いは、どうやって決まる?」という質問がありました。川島先生は「遺伝が2割、環境が8割」と回答していました。幼児を育む我々としては、上記の考え方を踏まえ、人的、物的環境を整備することで、子ども達の未来を育てていかなければならないと強く感じました。