
今回は、「こども誰でも通園制度」について、簡単に解説させていただきます。こども誰でも通園制度とは、保護者の就労有無や理由を問わず、0〜2歳の未就園児が保育施設(保育所、認定こども園、幼稚園)を時間単位で利用できる制度です。2023年6月に「こども未来戦略方針」のなかで打ち出され、2026年の本格始動を前に各地でモデル事業の実施や体制づくりが進められています。松戸市においてもモデル事業が進められています。
さて、これまで保育施設を利用するためには、保護者が働いているなど一定の条件を満たす必要がありました。しかし、こども誰でも通園制度は、保護者が専業主婦(夫)であっても、理由を問わず誰でも利用できるという制度です。
この制度のできた背景には、未就園児を育てる家庭では、核家族化や地域におけるつながりの希薄化などによる育児の孤立化があります。こうした子育て家庭における孤立感や不安感を軽減し、すべてのこどもの育ちを応援することを目的として、こども誰でも通園制度が創設されました。この制度を利用することで、こどもにとっては、家庭と異なる環境や人との関わりを経験することができ、成長を促すきっかけとなります。保護者にとっては、一時的に育児から離れることで、育児の孤立、不安感が軽減されるほか、保育者を通じてこどもの成長を実感したり、育児相談をしたりする機会が得られます。また、施設側にとっては、空いている施設の有効活用や、地域にいる要支援家庭の早期把握に貢献できるといわれています。
しかし、本格的な導入に向けて、数々の課題も指摘されています。保育するこどもが増えることにより、対応時間、労力、業務量が増加し、それらが負担となります。全国的に保育士等が不足するなか、負担の増加は最大の懸念事項といえます。また、在園児であれば、十分な時間をかけて、それぞれのこどもの特性や家庭状況を把握できます。しかし、1ヶ月10時間という上限があるなか、短時間でそれらを把握し、安全な保育を提供することはかなりハードルの高いことです。保護者にとっても、短時間でしかも限られた回数のなかで希望どおりの日程で利用できるのか、果たして育児の負担が軽くなるのか疑問が残ります。また、こどもが慣れるまでに時間がかかってしまい、家庭外で過ごす経験が充実したものにできるのかという不安も考えられます。他にも在園児の保育に支障を来さず、新制度を利用するこどもの安全を守るために、保育士の人員確保や保育環境の整備など検討すべき課題は数多くあります。さまざまな課題が解消され、保育者が専門性を発揮し、子育て家庭が孤立することのない事業運営ができるかどうか、我々も研修会を通して学んでいるところです。
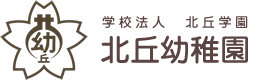
.jpg)


