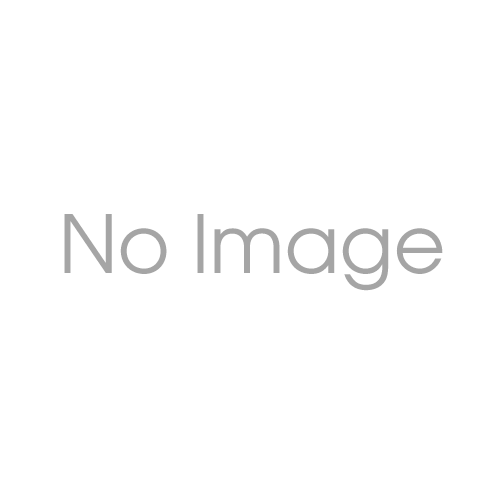
ウェルビーイング聞きなれない言葉ですが、最新教育動向2024という書物によると、「身体的、精神的、社会的に良い状態にあること」「将来にわたる持続的な幸せ」という意味で、経済協力開発機構(OECD)では、これからの人々や社会が目指すべきありさまとして提唱される概念となっています。ところで、国際的な調査において、日本の子どもたちは、先進国の中でウェルビーイングが低いと指摘されています。不登校やいじめ、貧困など過度のプレッシャーやストレス、人間関係の希薄化などが原因と考えられています。
ウェルビーイングを高めていくためには、大人が子どもの主体性や自己決定力を尊重し、興味や関心に応じた多様な活動を提供することが大切であるとされています。子どもたちの感情や気持ちを受け止め、共感や励ましを示すことで、自信や自尊心を育みます。また、子ども同士の交流を促し、友情や信頼を築くことも大切です。これにより、創造性や想像力が豊かになり、問題解決能力や感情調整能力が高まります。
子どものウェルビーイングを高めるためには、保護者のウェルビーイングを高めることが重要です。子どもの健康や発達だけでなく、保護者の幸せも重視することで、保護者の自信や満足感、仕事と家庭のバランス、社会的なつながりを高めることを目指しています。保護者と保育者との信頼関係の構築、保護者同士の交流や支援の促進、柔軟な保育サービスの提供により、保護者のウェルビーイングを向上させることができます。また、子どもたちを指導する教師・保育者のウェルビーイングを確保することも大事であるとされています。
京都大学の内田由紀子先生は、こうした学校を中心にしたウェルビーイングの高まりが将来にわたって世代を超えて循環していくという姿を目指していくことを求めています。北丘幼稚園としては、子どもたちが安心して過ごせる人的・物的な環境を作り、子どもたちを取り巻くすべての人々が笑顔で幸せに暮らせるように努めていきたいと思います。
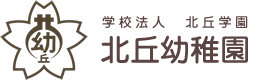

.jpg)

