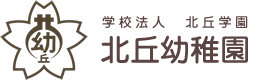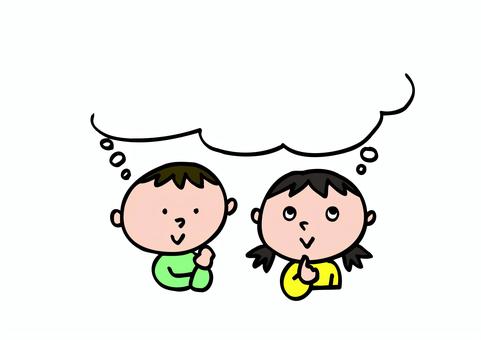
これは、石田勝紀さんの著書の題名です。学校で同じ勉強をしているのに、なぜできる人とできない人がいるのか。誰しもが一度は疑問に思うことではないでしょうか。その答えは、ずばり「考えること」をしてきたかどうか、親がさせてきたかどうかだそうです。小さいころから自然と考えることをしてきた人は、頭脳のスペックが高くなり、勉強だけでなく音楽、美術、体育そして、大人になってからは仕事もこなせる人間になっていくそうです。
2学期の終わりの頃の話ですが、幼稚園ですてきな光景を目にすることができました。それは、どうしたらお気に入りの段ボール(電車の絵が描いてある)をかぶって、颯爽と二輪のスクーターに乗れるかを必死に考え、試行錯誤する年少の男の子の姿です。スクーターに乗ってから段ボールを持ちあげようとすると、重くて持ち上げられません。スクーターを掲揚塔のポールで支えておいて、先にかぶってから乗ろうとすると前が見えずスクーターが倒れてしまいます。自分の頭をフル回転させ、何回も失敗を重ね、懸命に取り組む姿が見られました。私はこういうことが大事だと思っています。大人がすぐに手を貸し、答えを教えてあげていては、考える力は育っていきません。
石田勝紀さんは著書の中で、考える力を育てるために、疑問を持たせることの大切さを力説しています。そして、疑問を持たせる3つのマジックワードをあげています。
1 「なぜだろう?」(原因分析)
2 「どう思う?」(自己表現力)
3 「どうしたらいい?」(問題解決力)
どれも考えないと、答えにならない問いになっています。人に問えば、相手の頭脳が動き出し、自分に問えば、自律的に考える力がついてきます。人は問われることによって、考えるようになるものです。