
「子どものうそ」について、新聞記事が掲載されていました。子どもにうそをつかれて、ショックを受ける親は少なくないと思います。
公認心理士である佐藤めぐみさんは、以下のように記しています。子どもがうそをつく理由には、「叱られたくない」「面倒なことをやりたくない」などの理由があります。しかし、うそによって得をしたり、難を逃れたりできると、安易にうそをつくようになるため、うそをつく温床を作らないことが大切です。うそをついたときには、威圧的に攻めるのではなく、親の言動や家庭環境がうそを招いていないか振り返ります。うそをついた理由を聞いてもその場で答えることはなく、親子関係が悪くなるだけです。例えば、娘さんに「宿題は?」と聞くと、いつも「終わった」という返事だったとします。ところが、学校からの連絡で宿題を忘れたことがわかりました。その時に頭ごなしに怒るのではなく、まず親自身の家庭環境を振り返ります。パートの仕事に追われ、宿題の確認をおろそかにしていたことに気づき、一緒に宿題に取り組むことで、子どもがうそをつく必要のない環境を作りました。また、親も軽はずみなうそをつかないようにすることが大切です。「おもちゃを片付けられないなら捨てるよ」と言って、実行しないことを口にしていると、子どもは「うそを言ってもいいんだ」と思い込んでしまいます。
見過ごしてはいけないうそもあります。4から5歳になると、自分の立場を守るために、相手の状況を読み取り、事実と違うことを本当だと思わせる「意図的なうそ」をつくようになります。友達を傷つけるような「悪意のあるうそ」だとわかったときは、友達の気持ちを考えさせます。注意してもうそを繰り返す場合は、構って欲しいという寂しさを抱いていることも考えられます。安心して話をできる雰囲気を作って子どもの気持ちを一緒に考える必要があります。子どものうそは、脳が発達して社会性が身につき、複雑なことを言える力がつくほど成長した証でもあります。おしまいに子どもがうそをついたときの対応のポイントを記します。
- 必要以上に叱ったり、怒ったりしない。
- うそをついた背景を見直す。
- うそで傷つけられた相手の気持ちを考えさせる。
- 本当のことを話したときには褒める。
- 「成長した証し」と受け止める。
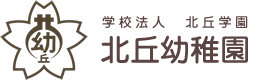
.jpg)


