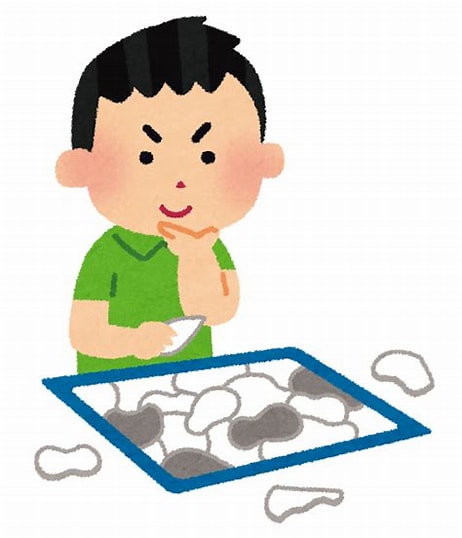
過日、「非認知能力を伸ばすコツ」と言う中山芳一さんの著書を読みました。以前よりこのコラムを通じて、非認知能力の大切さを訴えてきました。改めて非認知能力を定義すると、テストでは測れない能力で、コミュニケーション能力、自制心、思いやり、意欲、忍耐力など生きていくうえで大事な能力を指します。幼児教育の世界では、最も大事にすべきことであると私は思っております。今回は伸ばすコツということで、以下、中山氏の理論を記述したいと思います。
非認知能力は、自分自身の内面に関わる力です。ですから、自身の意識づけによって、高められます。例えば、話し合いの席で、「今日は意欲的に発言しよう」と意識して、話し合いに臨めば、望ましい行動が伴ってきます。自分自身の気の持ちようが大切です。また、相手(子どもや部下、後輩など)が非認知能力を伸ばしていくために環境となる大人ができることは何か?それはシンプルに「ほめること」「叱ること」です。その際には、つじつまが合い、一貫性がなくてはなりません。そして、ほめるときに最も大事なことは、結果ではなくその過程(プロセス)をほめることです。例えば、子どもが難しいパズルを完成させたとします。その時に「頑張ったね」と大雑把に伝えるのではなく、「おやつも食べるのも忘れて、1時間も集中して取り組むことができたね」と、そのパズルの完成させるために懸命に取り組んできた過程をほめて欲しいと思います。
ほめるためには、ほめる側が見取る力を養って、相手にフィードバックする必要があります。その時に大事になってくるのがタイミングです。相手の価値ある行動を即座にフィードバックすることです。例えば、子どもが親から借りたハサミを返しに来たとします。その子がハサミの持ち手の方をこちらに向けて返してくれた瞬間「よく持つ方を向けて返すことができたね」と声をかけます。見取ったことをすぐにフィードバックするわけです。このようにしていくと、行動が強化され、非認知能力を伸ばすことにつながります。
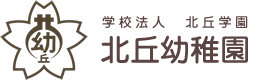

.jpg)

