
前回に引き続き、「学力テストでは測れない非認知能力が子どもを伸ばす」言う中山芳一さんの著書の中から、どうしたら、非認知能力を高めることができるのかについて、中山氏の理論について述べてみたいと思います。
まずは、土台となる自己肯定感(自己受容感)が子どもの育つ力の原点となります。幼児期前半までは、保護者をはじめとした他者からの愛着関係が何よりも大切です。肌と肌との関係だけでなく、言葉などを通じた呼びかけとその呼びかけに応じる呼応関係へと移行していきます。自分という存在が受け容れられているという経験が求められています。幼児期の後半からは、土台となる自己肯定感の上で、家の柱や筋交いとなるさまざまな非認知能力を獲得向上させていくことになります。これらは、教え込まれるというよりもさまざまな体験を通じて身につけていくものです。児童期になると屋根に当たる認知能力の獲得・向上の機会に出会えるようになってもらいたいものです。個人差はありますが、大人が勝手に焦って、土台や柱が十分でないのに屋根を取り付けようとしたら、その家はどうなるでしょうか。子どもを育てるために土台である自己肯定感を育み、その上に柱や筋交いである非認知能力を育み、そして屋根である認知能力を育むことの重要性を知っておくべきです。
非認知能力を育むには、まず、体験したことを自分の中で経験に変え、その経験を振り返ることが大切です。自然体験のような特別(非日常的)な体験だけではなく日常生活の中にある体験を経験や学びに変えていきたいものです。こうした体験をやりっぱなしにするのではなく、しっかりと振り返ることができれば、最終的に学びとなります。もうすぐ夏休み、さまざまな体験をして欲しいと思います。
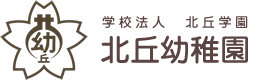

.jpg)

