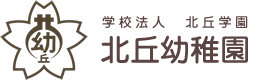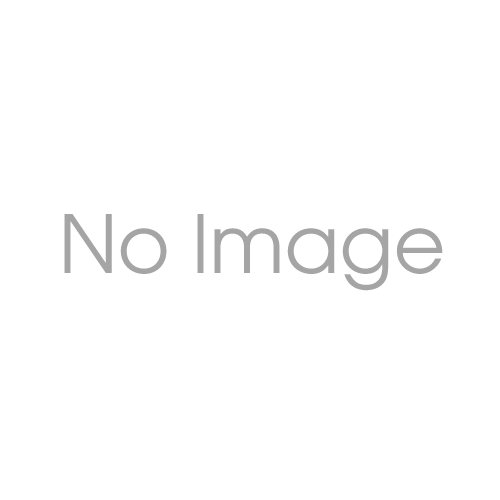物事を成し遂げるときにゴールを意識させ、見通しを持たせることは重要です。例を挙げて説明します。小学校での国語科の授業、昔は物語文や説明文の教材は文章からどんなことが読み取れるか、読解することに重きが置かれていました。しかし、今は本文を終えた後に感想文を書いたり、図鑑を作ったり、手紙を書いたりなど読み終えた後に行う学習を見据えて、本文を学んでいくというスタイルに様変わりしています。ですから、教師は単元の最初に読み終えた後に行うことを知らせたり、実際に作ったものを見せたりして動機づけを行います。体育科の跳び箱運動でも初めに上手な演技を教師やDVDなどで子どもたちに見せ、単元の終了時の目指す姿を提示し、見通しを持たせます。そして、ゴールの技ができるように日々の授業を組んでいきます。幼稚園でも母の日や父の日のプレゼントを作らせる際に今日の活動のゴールとなる見本を見せ、活動していきます。
2017年に幼稚園教育要領が改訂されました。今回の改定では、小学校以上との教育のつながりが大事にされています。そこで示されたのが、「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」です。これは、小学校入学前までに養っておきたい姿を10の項目を挙げ、幼稚園、保育所、認定こども園共通の指針とされています。
(1)健康な心と体
(2)自立心
(3)協同性
(4)道徳性・規範意識の芽生え
(5)社会生活との関わり
(6)思考力の芽生え
(7)自然との関わり・生命尊重
(8)数量・図形、文字等への関心・感覚
(9)言葉による伝え合い
(10)豊かな感性と表現
いずれの項目も育てるべき能力や目標といった達成を求められる課題ではなく、あくまで育ってほしい方向性を表したもので、生活や遊びの中で感性を働かせて良さや美しさを感じ取り、できることを工夫して使えるようにすることが重要とされています。