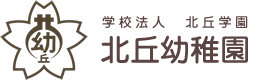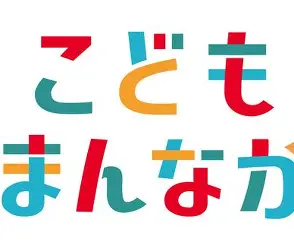「スマホはどこまで脳を壊すか」は東北大学応用認知神経科学センター助教である榊浩平先生の著書の題名です。3月に先生の講演を聞く機会がありました。ふだん、子どもたちの話を聞いていると、たくさんの情報をスマートフォンから得ていることがよくわかります。長時間ゲームに興じている子も少なくないようです。幼児期は脳が加速度的に発達していく時期です。習慣や環境がその形成に大きな影響を与える時期でもあります。その大切な時期にこれでいいのだろうかと少し心配になります。
スマートフォンの長時間使用は、学力や注意力の低下、依存症のリスクを高めるなどの負の可能性がたくさんあります。また、子どもたちが言葉を学び、コミュニケーション能力を育む大切な時期に、直接的な親子の対話や身体を使った遊びの時間が減少することも懸念されています。先生の講演の中で、スマートフォンの悪影響について、携帯性、依存性、多機能性に触れた部分がありました。話を聞いて特に私が気になったのは、依存性です。一つ動画を視聴し終わると、自分の趣味嗜好にあったものが次々と表示されます。ドラマを一つ見終わると、以前でしたら、また来週となるところですが、最新のものでなければいくらでも見ることができます。ゲームもなかなかやめることができません。自分自身で区切りをつけられないと、終わりがなくなってしまいます。
では、どうすればよいのでしょうか。当たり前のことですが、時間を制限することが大事です。スクリーンタイムを1日1時間以内に抑えるなどのルールを親子で決める必要があります。ちなみに1時間未満で終わりにできる子の一番学力が高いことが統計に表れています。それは、自分自身で制御できるからだと考えられます。また、スマホに頼らず、親子の関わりの時間を増やすことが大切です。特に読書や絵本の読み聞かせは脳にとって有益です。将来のある子どもたちが健康的に成長できるようサポートすることが、現代の保護者に求められています。スマートフォンは便利なツールですが、目的に合わせて適切に利用させていく必要がありそうです。